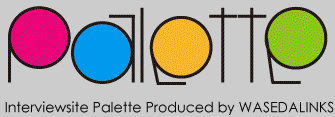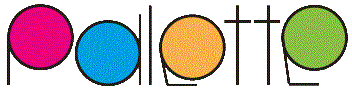「一般大学」という言葉は、ときに美術大学などの専門的な教育機関と比較する際に使われる。この呼称は、「一般大学」でデザインをしている人を、専門の世界から遠ざけているのではないか。
デザイナーとして、グラフィックデザインやwebデザインを数多く手掛ける有馬トモユキさんは、いわゆる「一般大学」を卒業した後、現在は日本デザインセンターに所属して、プロのデザイナーとして働いている。有馬さんはどうして「一般大学」からデザインの世界に入ったのか、「一般大学」では何を勉強したらいいのか、話を聞くことが出来た。
有馬トモユキ
1985年長崎県生まれのデザイナー。青山学院大学経営学部を卒業したのち複数の制作会社を経て、現在は日本デザインセンターに所属している。主にwebやグラフィックのデザインを手掛け、最近は「アルドノア・ゼロ」や「Fate/stay night[Unlimited Blade Works]」などアニメーション作品のデザインにも携わっている。また、音楽レーベル「GEOGRAPHIC」クリエイティブ・ディレクターや、SFレーベル「DAISYWORLD」主催、タイポグラフィ教育機関「新宿私塾朗文堂」講師として幅広く活動している。
――まずは、有馬さんの経歴についてお話を伺いたいと思います。デザイナーになるにあたって、いつごろデザインに興味を持ったのですか?
僕がwebのことを面白くてかっこいいものだと思いはじめたのは、1998年から2000年の頃で、僕は当時中学生でした。自分でwebページを作り始めたその頃、webデザインに携わっている人間の母数はとても少なくて、たぶん日本に50人もいなかったと思います。でも、僕にはそれが魅力的に見えました。なぜかというと、コミュニティが小さいために、会ったことがないにもかかわらず、お互いの作品や考えていることを知っているという密接な結びつきがあったからです。
――有馬さんは制作会社でのアルバイトからデザインの世界へ入っていったそうですが、どのような経緯でバイトを始めたのでしょうか?
高校生のとき、web制作会社の社長がうちで1回バイトでもしてみないか、と僕のホームページの掲示板に書き込んでくれたのがきっかけになりました。当時ならではの話ですよね。それで、その人に4、5年お世話になりました。
――時代の変化を感じる採用エピソードですね。でも、どうして美術大学に行かない一方で、制作会社でバイトをしようと思ったのですか?
現在iPhoneアプリについて専門で教えてくれる学校がないのと同じで、当時は僕の一番の関心領域であるwebを専門で教えてくれる学校は少なかったんです。webにおいては、テクノロジーが生まれてから、実際にweb制作会社が立ち上がって社会的な認知を得るまで、おそらく7年~8年くらいのラグがありました。そのボーナスタイムの間に、webに興味を持つようになったのは、運がいいのと同時にキツいことでもありました。誰に習えばいいのかわからないときだからこそ、美術大学に行くのではなく、制作会社でバイトをしながら実践的なデザインの技術を身に付けようと考えました。
――そういった経緯があって制作会社でのバイトを決断したのですね。制作会社でバイトをしていたのは4、5年ということなので、有馬さんが大学生のときでしょうか。
制作会社でのバイトと同時に、僕は青山学院大学の経営学部に通っていました。経営学部に進学したのは、デザインを依頼するクライアントの考え方に一番近い学問だと考えたからです。結果、クライアントとの打ち合わせで役に立っているので、この進路選択は正解だったと思います。


▲アルドノア・ゼロ ©Olympus Knights / Aniplex•Project AZ
【次ページへ】一般大学でできることとは